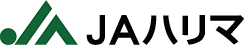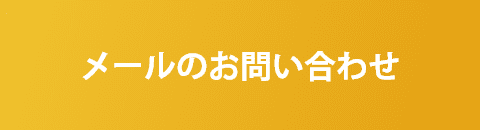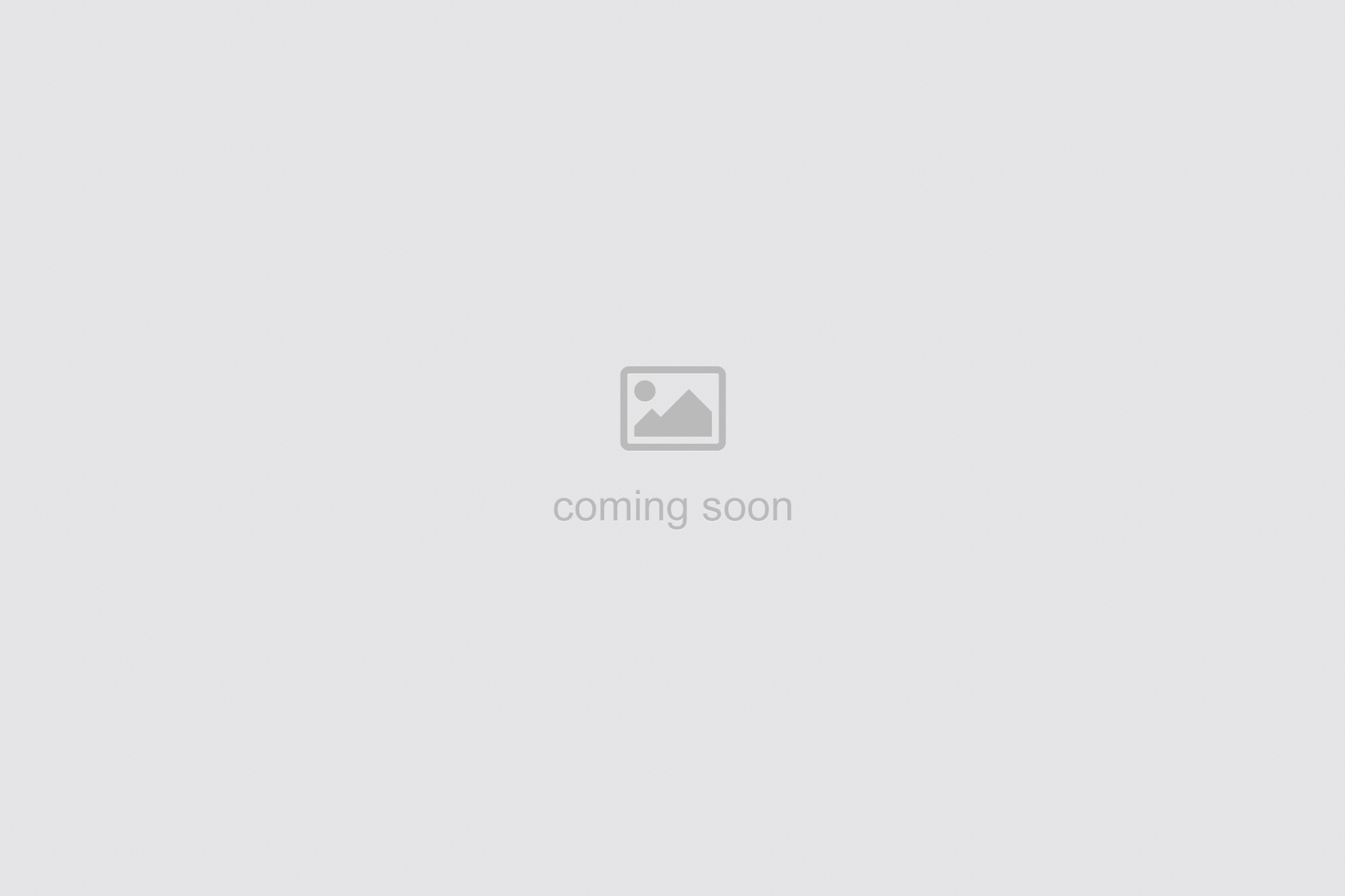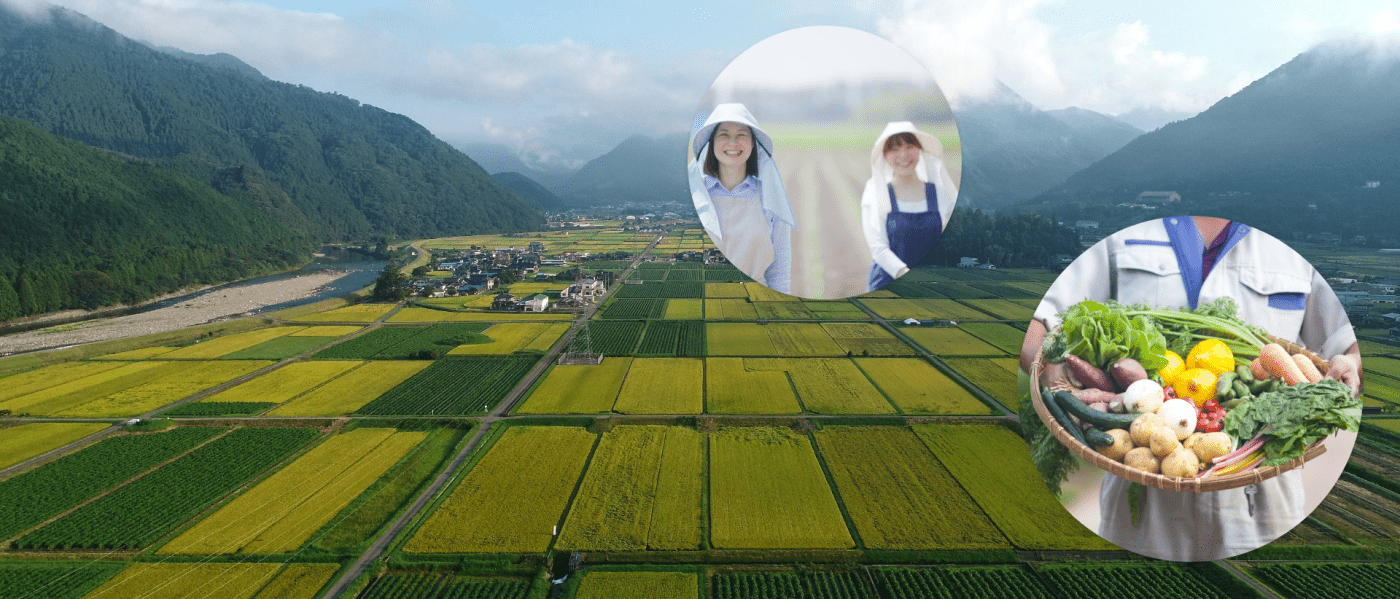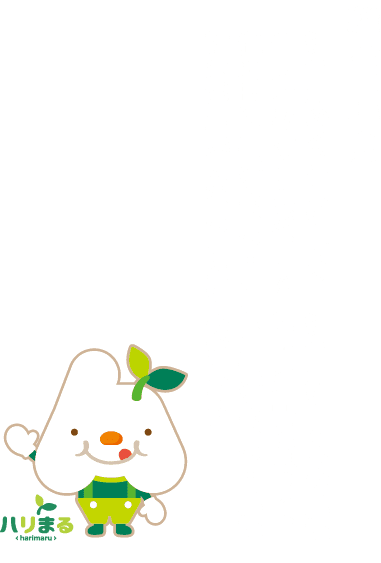新着情報とお知らせ
News & Topics
JAハリマの新着情報
2024-02-09
2023-12-11
2023-12-11
2023-12-01
2023-09-19
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
JAハリマからのお知らせ
2024-03-12
2024-01-15
2023-12-01
2023-08-01
2023-06-01
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
JA共済
JA共済は、JAが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆様の生命・傷害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。